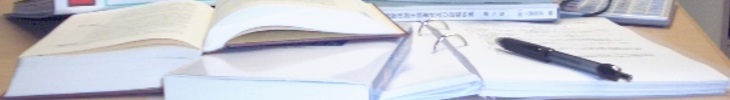離婚協議書の作成について 離婚協議書の作成について離婚届を市町村長に届け出る協議離婚は、当事者の協議による合意の上でするものです。
離婚の合意には、親権者の定め、養育費、面接交渉、離婚慰謝料、財産分与がありますが、このことを「離婚協議書」という文書にして残すことが大切です。
離婚の慰謝料とは、離婚について責任のある側が他方に支払う損害賠償です。財産分与とは、婚姻中に夫婦の努力によって形成された財産の清算です。
養育費とは、子を引き取って養育する親に対して、他方の親から子の養育の費用として給付するものです。
離婚給付と養育費の定めを公正証書にして活用することができます。これを「離婚給付等契約公正証書」といいます。相手方が支払を履行しないときには強制執行が可能になります。
離婚協議書作成の詳細はこちらです
 公正証書遺言の作成について 公正証書遺言の作成について
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成するものです。
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
法務大臣が任命した公証人が作成するもので、確実なことから広く行われています。
公正証書遺言には、必ず2人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。遺言者の第一順位の推定相続人及び受遺者並びにそれらの者の配偶者と直系血族は証人になれません。当事務所の行政書士は、平塚公証役場において証人を引き受けることがあります。
公正証書遺言書の詳細はこちらです
 遺産分割協議書の作成について 遺産分割協議書の作成について
相続の手続をするには遺産分割協議書の作成が必要です。相続の登記も相続税の申告にも必要となります。
相続開始から10ヶ月以内に作成して相続税の申告をすれば、配偶者控除、小規模宅地等の評価減の特例を受けることができますのでなるべく早く作成した方が良いです。
遺産分割協議は相続人が1人でも欠けて行われた場合には無効ですので、相続人の確認から始めます。被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人の有無を確認します。
被相続人の遺言書があることが判明した場合には、家庭裁判所で検認を受けます。
※公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
被相続人の遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作成します。
その後、相続人全員で遺産の分割を協議して、分割の協議が成立した場合に、この「遺産分割協議書」を作成することになります。銀行や相続登記申請の際に法務局に提出することになります。
なお、相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
遺産分割協議書は、住民票、除籍・戸籍謄本とともに、相続登記の際に「相続を証明する書類」のひとつになります。除籍や戸籍謄本は、原則として亡くなった方が生まれた時点から亡くなるまでのもの全てが必要となります。
遺産分割協議書の詳細はこちらです
|